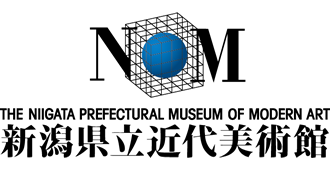学芸員コラム34 追憶の眼差し―《ベンガル虎 バッカス祭》
2024年10月18日
「歴史的な評価がさだまっている作家」という表現を時々使うことがあります。作品についても同様の言い方が可能でしょう。厳密に定義することは難しくとも、共通認識としていくつか価値判断の基準があり、それを満たしていれば使ってもよいものとみなして比較的ゆるやかに用いているものだと思います。たとえばある作品を作家がしかるべき展覧会に出品していれば、作家本人による担保が付されていることになり、「〇〇展出品作」という称号が与えられ、安心して紹介できます。何らかの賞を受賞していれば、画壇のお墨付きが得られた作品として堂々と押し出せます。あるいは作家の作風上の転機となった作品であることや、美術史上のエポックメーキングな作品であることが研究によって立証され、その後の回顧展にも出品されて大勢の目に触れてイメージが浸透していくなどして、徐々にステータスが上がっていく場合もあります。専門家の評価と世間の支持が結びついて一般に根付いていく感じでしょうか。
一方で、当然のことですが「歴史的な評価がさだまっていない作品」というものもあります。現在開催中の「日本が見たドニ|ドニの見た日本」でドニ後半生の大作として紹介している《ベンガル虎 バッカス祭》(1920年 新潟県立近代美術館・万代島美術館)は、この観点からみて非常に興味深い問題を孕んでいます。

モーリス・ドニ《ベンガル虎 バッカス祭》1920年 新潟県立近代美術館・万代島美術館
およそ100年前に制作され、パリのサロン・ドートンヌに作家が出品したとされるものであり、「歴史的な評価がさだまっている作品」と呼ばれ得る資格は満たしています。しかし、作品が今日までたどってきた道のりは決して平坦なものではありませんでした。もともとスイスのジュネーヴにある「ベンガル虎」という毛皮店の注文を受けてドニが制作し、店内に設置されていた装飾画です。1980年代の絵画市場に姿を現し、その後海を渡ってアメリカのコレクターが所有するところとなりました。一説によると、その時、家に入らないからという理由で画面は大きく二つに分割されてしまいました。あくまでも仮定の話ですが、もし作品の歴史的な評価がさだまっていたら、コレクターは自宅のサイズに絵画を合わせるのではなく、自宅の方を改築して間口を広くすることを考えたのではないでしょうか。数年後、二画面となったバッカス祭は再び売りに出され、別々の所有者の手にわたりましたが、幸いにも一人の所有者によって左右両方が収集されました。日本の画商を経由して作品購入のオファーが当館にあり、2001年に新潟県が収集したことで、作品の長い旅路(流浪?)に一応の終止符が打たれました。

モーリス・ドニ《ベンガル虎 バッカス祭》(部分)
あらためて大きな一画面として作品を眺めてみると、バッカス祭という画題にふさわしく、賑やかな光景が繰り広げられています。注文主を象徴する虎やさまざまな動物が生き生きと描かれ、またドニの作品らしくかけがえのない家族の姿がそこにあり、特に子供の笑顔が作品に力強い輝きを与えています。では一点の曇りもない晴れやかな場面かといえばそうではありません。自然の恵みに歓喜する宴にそぐわない表情をした人物が一人描かれています。
二頭のヒョウにひかれた車の上にいる酒の神バッカスです。本来の主人公が、少し後景に退いた位置におり、子どもたちがいる方向を振り返っています。その曖昧な表情は、微笑んでいるようにも、物思いに沈んでいるようにも見えます。静かに振り返る身振りとやや伏目になった視線は、目の前のものを見るというよりも、そこにはない何かに向かっていく心を想起させます。ドニは前年妻マルトを失ったばかりでした。このバッカスの眼差しには、彼女がいた日々のことを追憶する作家自身の心情が投影されていると考えることは決して的外れではないでしょう。生命の輝きと幸福感に満ちている作品ですが、バッカスの追憶の眼差しはその奥に何かが秘められていることを暗示しており、一元的な解釈を下すことを思いとどまらせます。「歴史的に評価のさだまっている作品」という表現は余計な説明のいらない重宝なものですが、こうした作品を前にすると、歴史的な評価とは何か、作品の真の意味とは何か、さまざまなことを考えさせる言葉でもあります。(専門学芸員 平石昌子)