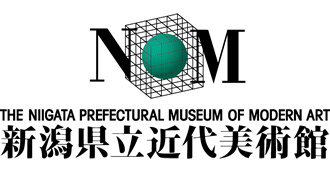この1点⑦ デューラー《メレンコリアⅠ》からつながる点と点
2020年11月01日
トピックスでは「この1点」と題して、当館のコレクションについて、「作品解説会」以上、「美術鑑賞講座」未満の少しディープなお話を紹介していきます。
1月から始まるコレクション展第4期「ルネサンスの版画」では、当館が所蔵するアルブレヒト・デューラーの版画作品を全点一挙に展示します。近代美術館にルネサンスの版画?デューラー?と思いますが、当館の西洋版画のコレクションは、「近代」へ至る道のりを通史として示すという方針のもと作品が収集されており、これらの版画作品は、当館コレクションにおいて、長大な西洋美術の歴史の始点に位置づけられています。
アルブレヒト・デューラー(1471-1528)は、ドイツ・ルネサンスを代表する芸術家であり、油彩画だけでなく、版画によって当時のヨーロッパで広く名声を得ることに成功しました。《メレンコリアⅠ》は彼の代表作であり、「西洋版画史上最大の傑作」と言われるほど重要な作品です。タイトルの「メレンコリア(メランコリー)」とは、古代ギリシャ以来の考え方で、人間の四気質の中の一つとされる憂鬱質を意味します。画中左上に飛んでいる獣が抱える銘板に記され、さらに、中央に座る有翼の人物像がとる左ひじを膝にあてて頬杖をつくポーズも、この憂鬱質を示す典型的な図像です。ルネサンスの学者たちは、古来マイナスな性質と見られていたこの憂鬱質を、思索に耽る芸術家や学者の知的活動と結び付け、必要不可欠なものとして好意的に捉えるようになりました。当時の時代状況、作中の銘文と中心人物の図像、ここまでは一貫した解釈の手がかりが揃っているように思われます。
 アルブレヒト・デューラー《メレンコリアⅠ》1514年 |
それにも関わらず、本作は制作されて500年以上を経てもなお、解決をみない謎が多く、多種多様な解釈がなされ続けています。それは一つ一つ意味深なモティーフが大量に描き込まれていることに由来しています。最近もこのモティーフの一つを取り出し、興味深い指摘がなされました。それは、画面の左側中央に置かれた多面体に髑髏を思わせる染みが見えるというものです(佐藤直樹「「自然」写実から潜在イメージへ」『アルブレヒト・デューラー版画・素描展』国立西洋美術館、2010年)。いまでも新たな解釈の可能性をいくつも開くような指摘がでてくること、まずはこのこと自体が本作の魅力の一つであることは間違いありません。
さらに、この染みは、以前の「この1点」でとりあげられていたコロー《ビブリ》における「チャンス・イメージ」の系譜に連なるものと言えるでしょう。「チャンス・イメージ」とは、自然の中に偶然見つけられるイメージのことで、デューラーはまだ若い頃に、枕の皺が顔に見えることに偶然気がつき、それを素描として残しました。デューラー自身がこうしたことへ言及したものは知られていません。しかし、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチは、汚れた壁の染みや色大理石の模様にイメージを見つけることについて書き記しており、19世紀の画家コローまで続く「チャンス・イメージ」の伝統がルネサンス期にも息づいていたことが伝わります。時代も地域も異なるこの2点の作品が、長い西洋美術の伝統をたしかに共有していることを感じさせます。デューラーもコローもそうした伝統の中に身をおき、制作を行っていました。そんな時、新潟で出会った2点の作品に、思わぬところでつながりが生まれます。1点でも十分に魅力的な作品同士に、ここでしか生まれ得ないつながりが見えたとき、その巡りあわせに思いをはせることも、コレクションの醍醐味ではないかと思うのです。
美術学芸員・松本奈穂子