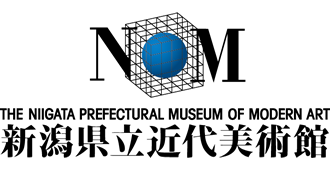この1点⑥ 鮭遡上の季節
2020年10月01日
トピックスでは「この1点」と題して、当館のコレクションについて、「作品解説会」以上、「美術鑑賞講座」未満の少しディープなお話を紹介していきます。
10月――鮭が産卵のために川を上りはじめるこの時期。
彫刻家・羽下修三(1891~1975)は、本職である彫刻の仕事も手につかないくらいになり、漁期の間は、もっぱら鮭捕りに没頭したといいます。
新潟県中蒲原郡川内村川内(現・五泉市)。阿賀野川に注ぐ早出川の流れる自然豊かな地域に、羽下は生まれました。手先が器用で、幼い頃から完成度の高い小品を彫り上げ、周囲を驚かせていた羽下は、彫刻家を志し、東京美術学校(現・東京藝術大学)彫刻科に入学します。木彫部は羽下一人という状況でしたが、高村光雲、関野聖雲、北村西望らの指導を受け、実力を身につけていきます。卒業後は東洋的な要素を取り入れた、モダンな雰囲気のする女性像などを制作し、官展を中心に活躍、地位を確立していきます。
1945年(昭和20)、羽下は東京の自宅を引き払い五泉に疎開します。戦後は同地の三本木にアトリエを建て、県内を中心に活動を再開していきます。しかし終戦直後は彫刻に使用する材料も思うように手に入らず、釣りを友に過ごしていました。幼い頃から早出川での漁の様子を見知っていたからか、とくに鮭捕りに関しては、羽下は強いこだわりを持っていたようです。漁具は自ら考案するほどで、鮭に関する知識も豊富でした。「鮭捕りでは、この方面の本職の漁師さえ、羽下を名人あつかいした程であった」(「小林存と羽下修三の鮭問答」『小林存伝』)というから、相当に精通していたようです。羽下は毎年10月になると三本木の自宅から早出川に出かけ、泊まり込みで鮭漁にいそしみました。
羽下が1953年(昭和28)の日展に出品した《鮭遡上》は、そんな彼の自叙的作品と言えるでしょう。防寒具をまといヤスを握る漁師の姿を、簡潔かつ明確な彫りによって表現し、既に熟練の域に達した羽下の技量を感じさせます。堂々と立つ漁師の面持ちは神妙でもあり、鑿跡の残る粗い表面も相まって、練達の漁師の気迫を感じさせます。その様相には、自身も豊富な経験を積んだ“漁師”であった羽下自身の姿が重なります。
 羽下修三《鮭遡上》 1953年(昭和28) |
さて、1958年(昭和33)、羽下は釣り上げた魚たちを供養するために、供養碑を自宅アトリエの前に建立しています(現在は五泉八幡宮内に移設)。自然石に「吊魚」と彫られた簡素な碑ですが、象形文字で現された「魚」の文字が大きく配され躍動しています。自身の人生にとって切り離すことのできない魚たちと、またそれを包括する故郷の豊かな自然への、羽下の深い敬意が感じられます。
季節は次第に冬へと向かいます。羽下が心躍らせた、鮭遡上の季節がやってきます。
主任学芸員 伊澤朋美