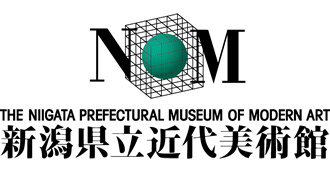この1点④ カミーユ・コロー《ビブリ》 テーマをめぐる謎
2020年08月01日
トピックスでは「この1点」と題して、当館のコレクションについて、「作品解説会」以上、「美術鑑賞講座」未満の少しディープなお話を紹介していきます。
近代美術館の名品として親しまれているカミーユ・コローの《ビブリ》は、画家が最晩年に情熱を傾けて描いた作品です。1873年10月にバレエ『泉』の舞台を観て、心を動かされたことが、この作品を構想する大きなきっかけとなったそうです。制作は74年から75年にかけて行われました。75年の2月、コローが息をひきとる二週間ほど前に、美術史家のエティエンヌ・モロー=ネラトンが病床の画家を訪ねた時の様子がモロー=ネラトンのつけていた日記から分かっています。《ビブリ》の話題に触れると、コローは「あれには皆さん大変満足しているようですね」と語ったといいます。そして画家の没後まもなく、作品は同年のサロンに、生涯最後の出品作の一点として展示されました。一枚の絵画が誕生する発端から、作品の仕上がりに対する人々の反応を語る作家の言葉まで、貴重な証言のいくつかが私たちの手に残されていることになります。そうしたエピソードを作品とともに味わうことができるのは、極めて幸運なことです。

カミーユ・コロー《ビブリ》1874-75年
ところで、この作品は成り立ちが比較的はっきりしているにもかかわらず、核心的な部分は深い謎に包まれています。そもそも、《ビブリ》という作品が、どのような主題を表しているのか、明確にはまだわかっていないのです。コローがバレエ『泉』の舞台からインスピレーションを得たのがことの始まりでしたが、当の作品には《ビブリ》というタイトルが与えられています。ビブリといえば、古代ローマの詩人オウィディウスによる『変身物語』に収められた「ビブリとカウノス」の話が想起されます。妹ビブリは双子の兄カウノスを激しく恋慕しますが、それを恐れたカウノスは他国に逃れます。兄を追って山野をさまよったビブリはついに森のはずれで力尽き、涙を流しながら泉に変容したという悲恋の物語です。コローの絵画を見ると、画面左奥の方に女性が倒れており、そこからひとすじの水路が流れ出ています。彼女を包むように、森の奥から闇が迫り、真珠色の雲が水平線までたなびいて、光と影の見事なコントラストをなしています。
一方、バレエ『泉』は、泉の妖精ナイラの物語です。ナイラは猟師のジェミルを慕いますが、ジェミルとグルジアの姫との恋を成就させるために身を引き、自らは犠牲となります。ナイラの死とともに、泉もまた涸れていきました。コローは泉の妖精に触発されて作品を描き始めたものの、その過程で、もう一つの泉の悲劇にたどりつき、最終的な作品タイトルをビブリと名付けたのでしょうか。作品の中には、悲恋の末に落命した二人のヒロインの姿が重ね合わされているようにも思われます。
ただし、ここで見落としてはならないのは、「ビブリ」という言葉には複数の意味があり、古代の港町の名前だという意見やキリスト教の殉教者の名前だという意見など諸説あるという点です。そのことが作品の典拠を今日なお特定できない要因の一つともなっています。
「ビブリ」というタイトルに、コローはどのような意味を込めたのでしょう。この絵画には一体どのような物語が紡がれているのでしょうか。主題を読み解いていくための一つの鍵となり得るものが作品の中に描かれています。《ビブリ》という作品の画面右横の大きな岩をよく見てください。そこに女性の顔が描きこまれていることがわかります。伏し目がちの女性の顔立ちやあごのラインが極めて繊細に描き出されています。岩と女性の顔は、絶妙なバランスを保って一つのイメージの中に共存しています。樹木は頭髪のようであり、岩肌を這う蔓草は女性の髪飾りのようです。研究者によって、《ビブリ》の岩の中に女性の顔が見えることはこれまで何度か指摘されてきました。西洋美術の伝統においては、自然の素材(岩、雲、染みなど)の中に人間にとって意味のある形象を読み取ることは古典古代から行われてきました。自然界に偶然見出された形、もしくはそれを自然物に見せかけて意図的に作り出した形のことを示す「チャンス・イメージ」という言葉があります(H. W. ジャンソン/J.ビアウォストツキ『イコノゲネシス』)。《ビブリ》に見られる女性の顔は、まさにこのチャンス・イメージである可能性が高いと思われます。何らかの意味を帯びた形を、他人に気づかれにくい方法でコロー自身が描きこんだのだとしたら、そこに真の意図が隠されていると推測することは十分可能だといえるでしょう。物悲しげな表情を浮かべた女性に注視してみることは、今後この謎めいた作品を解釈していくうえで、有効なのではないでしょうか。
専門学芸員・平石昌子