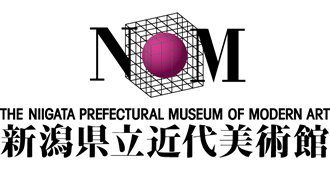この1点⑫ 佐々木象堂《鋳銀馬置物》(1933)をめぐって
2021年05月01日
トピックスでは「この1点」と題して、当館のコレクションについて、「作品解説会」以上、「美術鑑賞講座」未満の少しディープなお話を紹介していきます。
佐々木象堂《鋳銀馬置物》(1933)※1をめぐって
本作は「蝋型鋳造」の分野で重要無形文化財保持者の認定を受けた、いわゆる「人間国宝」となった佐々木象堂の作品です。佐々木象堂は1882年に佐渡市に生まれ、20歳の時に初代宮田藍堂から蝋型鋳金を学び、1913年上京、以降、新しい時代の息吹を受けながら、1944年に東京を離れるまで、斬新な作品を制作し続けました。これは佐々木象堂に限ったことではありませんでした。当時はヨーロッパのアール・ヌーヴォーやアール・デコといった新思潮に感化された若い工芸家たちが、新時代にふさわしい工芸を生みだそうと躍起になっていた、言わば、モダニズムの時代でもあったからです。
さて、この本作ですが、鞍をつけ、前足と後ろ足をきちんと揃え、お行儀良くじっとしている様のお馬さんが、きわめてリアルに表現されています。普通にみると、これが斬新な工芸?という気になります。確かにあまり象堂らしくない作品です。
象堂らしさと言えば、例えば、動物の特徴を的確に捉えながらも、その造形を直線と曲線で再構成してシャープな感覚で仕上げた《鋳銀孔雀香爐》(1927)や《兎(鋳銀置物)》(1928)、あるいは伝説の鳥、鳳凰の動きを大胆にダイナミックに表現した《金銅鳳凰置物》(1929)などに比べると、大人しすぎて随分と普通の馬に見えてしまいます。
しかし、あらためて本作を眺めてみると、力を蓄えながらも太く短い足、馬自体もスマートではありません。また鞍をはじめ装飾物も見慣れないものです。そう、これは現在のサラブレッドのような駿馬ではなく、日本古来の馬の姿であり、頭(こうべ)を垂れ伏せられた眼(まなこ)は遥か悠久の歴史を想っているかのようです。
象堂は1930年11月に鋳金の仲間とともに奈良へ旅行します。その時に幸運にも正倉院宝庫にて御物の拝観を許されたといいます。そこで接した正倉院御物、いわゆる天平文化の粋を集めた凄さに象堂は打ちのめされました。その圧倒的な衝撃が新たな創作意欲に繫がり、それまでの作風を転換し、天平文化に端を発する本作《鋳銀馬置物》制作の動機になりました。それが、やがて《鋳銅飛天置物》(1934)、《彈阮咸鋳銅置物》(1937)、そして人間国宝として認められるきっかけとなった、晩年の傑作《蝋型鋳銅置物瑞鳥》(1958)や《蝋型鋳銅置物采花》(1959)制作にも生かされていくことになります。その意味ではヨーロッパ起源となる構成主義的な作品を制作していた象堂の、大きなターニングポイントとなった作品でもあり、重要な意味を持つ作品でもあります。
なお、象堂は本作を余程気に入ったらしく、銅で本作と同型のものを制作し、その表面に金箔を置き古色を演出した《金銅飾馬置物》(1936)※2を東京府美術館の第2回越佐展に発表。さらに造形に動きを持たせた銅の古式飾馬に、《鋳銅色絵鸚哥置物》(1940)※4で使用した、象堂自身、初の試みとなる色絵銅を再度用いて、《駃騠鋳銅色絵置物》(1942)※3を第5回新文展に発表しています。とは言え、当時の批評を見ると「馬の形が整はず」と象堂の意図は当時も理解されなかったようです。
閑話休題。すでに名声を得ていた佐々木象堂にも、大きな影響を与えることになった正倉院御物の素晴らしさは如何ばかりというところですが、その天平文化を再現した逸品がこの夏、新潟県立近代美術館にやってきます。当館も新型コロナウイルス感染拡大防止対策も心掛けてまいりますので、皆様もご注意しながら、この貴重な機会をお見逃しなく。
(学芸課長 藤田裕彦)

鋳銀馬置物 ※1

金銅飾馬置物 ※2

駃騠鋳銅色絵置物 ※3

鋳銅色絵鸚哥置物 ※4 当館蔵