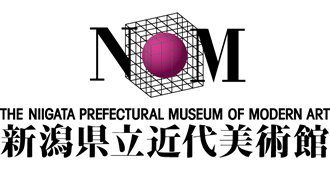この1点⑪ ジュリアン・デュプレ《羊飼い》―なぜ、ボロボロのマントを着ているの?
2021年04月01日
トピックスでは「この1点」と題して、当館のコレクションについて、「作品解説会」以上、「美術鑑賞講座」未満の少しディープなお話を紹介していきます。
ジュリアン・デュプレの《羊飼い》は、当館コレクションの中でも幅広い年齢層の皆さんから愛されている作品です。ある時、この絵が好きだという方にその理由を聞くと、「絵の中に入っていけそうな気がする」とおっしゃっていました。縦が148㎝、横が207㎝とサイズが大きいため、その前に立つと、平原を満たしている空気や光までが感じられます。自分が羊飼いになったつもりで、羊たちが静かに草を食む風景を眺めていることを想像するとどうでしょう。時間が経つのも忘れてしまいそうです。もちろん画寸の大きさだけが魅力ではありません。細部の描写に惹き込まれたという学校の生徒さんたちもおられます。画面を手前の方から注意深く観察していくと、地面に生えた雑草の少し硬そうな手触りや、野生のアザミの鋭い棘、ぼさぼさにからまった犬の黒い毛並み、羊の埃っぽくて厚みのある毛など、驚くほどのリアリティがこちらに迫ってきます。絵のすみずみまで思わず感嘆するほど見事な描写や質感で満ち満ちています。

ジュリアン・デュプレ《羊飼い》1883年
一見分かりやすく誰にでも親しみやすい作品―本当にそうでしょうか。もしそれだけだったら、これほど長く幅広い人気を誇る作品となり得たでしょうか?この作品には、おそらく観る人の心を惹きつける何かがもっとあるのではないか―そんな気がしてきます。そしてその鍵を握っているのは、間違いなく、絵の主人公であり主題である羊飼いでしょう。子細に見ていくと、かなり神秘的な存在として描かれていることがわかります。つば広の帽子を目深に被り、四分の三後ろ正面の角度から描かれているので顔は殆ど見えません。年齢も分かりません。身体を覆っている重そうなマントは相当年季が入っていて裾に大きな穴があり、継ぎ接ぎがされています。穿いている靴も幾年にもわたり荒れ地を踏み越えてきたのか、もはや大地の一部と化しているようです。全身が激しく何かを物語っていますが、なかでも特に目を奪われるのはマントです。なぜこんなにボロボロなのでしょう。
羊飼いのマントが目につくほど傷んでいることの背景には、少なくとも二つの可能性があると思われます。一つは、羊飼いという職業に由来するものです。古来、西欧世界では羊飼いという職業は苛酷な仕事の典型として知られていました。何か月もの間誰とも会わず、羊たちを守る孤独な仕事です。野宿をする夜には狼などの猛獣の脅威もあったでしょう。群れからはぐれた羊を探すために危険に身をさらすことも稀ではありませんでした。キリスト教の聖書の中では、羊を信者に羊飼いをキリストにたとえるエピソードが語られています。羊飼いは、キリストが民のためにそうしたように自らを犠牲にする役割を担い、貧しく、厳しい自然との対峙を強いられる仕事でもあったのです。無惨に破れたマントは、その民族的な歴史を象徴しているものだといえるでしょう。
もう一つの可能性は、この羊飼いをある物語の主人公ではないかとする説からきています。17世紀のフランス詩人ラ・フォンテーヌが書いた『寓話』のなかに、「羊飼いと海」という物語があります。一人の羊飼いがおりました。ある時船を見て、一山当ててやろうという野心を抱き、羊を売り払って商売を始めました。ところが嵐に遭って積み荷を全て失い、極貧の身に落ちぶれました。苦労して少しずつ羊を買い戻したある日、海に船が再び近づいてくるのを見て、男はこう言いました。「誰か他のやつに掛け合ってくれ!」と。デュプレの作品に改めて目を凝らすと、右上方に黄色味がかった水平線のようなものが見えます。これが海(入り江)だとすると、「羊飼いと海」の舞台背景であるという解釈ができそうです。マントの傷は、嵐の海での壮絶な体験の記憶をとどめているのかも知れません。男の視線は羊の群れを見ており、海の方を見ているわけではありませんが。かつて冒険心にかられ、手放したこのささやかな日常を、羊飼いは今どのような思いで見つめているのでしょうか。
デュプレは、この作品にただ《羊飼い》という題名を与えました。なぜ羊飼いはボロボロのマントを着ているのか―その答えはまだ見つかっていません。謎は依然として謎であり、これからも観る人の興味をかきたてることでしょう。そんなことを思いながら、絵の前にたたずんでいると、時おり潮風の香がかすかに漂ってくるような気がします。(専門学芸員 平石昌子)
参考文献:『自然に帰れ―ミレーと農民画の伝統』山梨県立美術館 1998年