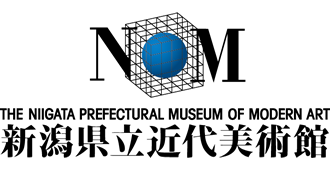学芸員コラム42 「博物館・美術館等保存担当学芸員研修」に参加して
2025年10月08日
今年の夏、美術館をちょっと離れて、とある研修に参加してきました。文化財活用センター(通称・ぶんかつ)が主催する「博物館・美術館等保存担当学芸員研修(基礎コース)」という研修です。東京・上野の黒田記念館を会場に、各地から集まった美術館・博物館の学芸員の皆さんと一緒に、5日間にわたって講義を受けました。この研修では簡単に言うと、「文化財を良好な状態のまま未来へと伝えていくための知識や方法」を学びます。大きな美術館の中には作品の保存を専門とする職員が配置されているところもありますが、残念ながら当館には専任の職員がいません。私自身は日頃の業務の中でつちかった知識の範囲で作品の保存について考えてきましたが、今回の研修をとおして、より専門的かつ実践的な知識や方法を学ぶことができました。
そもそも、美術館の学芸員の仕事は展覧会を開いて作品を「展示・公開」するだけではありません。美術館で持っている美術作品を「大切に保存して、未来へと伝えていく」ということも大変重要な仕事です。ところが、作品を「展示すること」と「保存していくこと」というのは、矛盾する行為でもあるのです。作品をそのままの良好な状態で保存するには、全く展示せずに人目に触れない真っ暗な収蔵庫の中に静かにしまいこんでおくのが一番よいのです。しかしながら、当館で所蔵しているコレクションは、新潟県民の財産でもありますから、多くの方に作品を見てもらい、楽しんでもらわなくては、宝の持ち腐れになってしまいます。つまり、「保存すること」と同時に「活用すること」も考えていく必要があるのです。
さて、日本には、文化財を保護するための法律、「文化財保護法」があります。
第1条
この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
第4条 第2項
文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
このように、「保存と活用の両立」は、法律にもしっかりと定められているのです。しかしながら、多くの学芸員は、「保存」と「活用」の間で、ジレンマを抱えながら日々仕事をしているのではないでしょうか。優れた美術作品をできるだけ多くの人に見てもらいたい、でも、作品をずっと展示することはそれだけ作品にリスクを負わせることになる……。そのため、学芸員は保存と活用のバランスを考えながら業務にあたっています。科学的な根拠にもとづいて、美術作品が日常的に置かれる環境を快適な状態に維持し、時には「保存」を優先するために「活用」に対して適度な制限を設けるなどしているのです。
さて、美術作品の保存に関わってくる要因には次のようなものがあります。
・温度と湿度
・空気環境
・照明(光)
・虫・カビなどの生物
・自然災害
・人為的な災害
展覧会に来られたお客さんから「展示室が寒い」「照明が暗くて作品がよく見えない」などの声をいただくことがよくあります。作品にとって適切な条件を優先しつつ、人間も活動可能な環境を追求した結果、美術館では温度は22℃、湿度は55%を基本に空調がコントロールされています。照明についても、強すぎる光は作品の変色を引き起こす原因になるので、作品の素材や制作年代などを考慮した上で適切な照度を決め、「照度計」という道具を使って光の明るさを測りながら調節しています。
また、空気中には様々な物質が浮遊していますが、中には有機酸やアンモニアなど、美術作品の劣化を引き起こす原因となるものもあります。目に見えないこうした物質が展示室内や展示ケース内に存在していないか、専用の道具(例えば、パッシブインジケータなど)を使って測定し、必要な対策をとっています(写真)。
ほとんどの美術館・博物館の展示室内は飲食禁止です。これも文化財を汚さないためであることはもちろんのこと、食べ物のカスが虫を呼ぶリスクを避けるためでもあります。美術作品を虫が食べてしまったり、糞で汚損したり、カビが生えてしまったりと、生物被害は一度起きてしまうと、気づいたときには甚大な被害になっていることが多いので、日頃の予防が大事なのです。これまで美術館では生物被害から作品を守るために、ガスによる燻蒸で虫やカビを一気に駆除する作業を行っていました。しかし、これまで使用してきたエキヒュームSという燻蒸ガスが環境への影響などを理由に2025年3月で販売中止となり、当館を含め、全国の美術館・博物館がそれぞれ新たな方策をとる必要に迫られています。
また、近年は気候変動の影響でこれまで想定していなかったような規模の自然災害がいつ身近で起きてもおかしくない状況になってきています。当館のすぐ近くには信濃川が流れています。地震だけではなく水害についても、日頃からリスクを想定して、対策を考えておかなければならないでしょう。
今回の研修をとおして、学芸員自身が自館の状況を日頃から観察・記録し、その特性を把握することが作品保存の第一歩であると感じました。そして、そこから見えてきた課題を解決するための方法を各館の事情に応じて取捨選択するのです。それでも美術館が抱える様々なリスクに日頃から備えておくのはなかなか大変なことです。温湿度管理など日頃からコツコツとやっていることに加えて、建物の修繕や消防・空調設備の更新、照明のLED化なども含めて、美術館がこれまでやってきたこと、そして今後も継続してやっていかなくてはいけないことは山のようにあります。いずれも美術館が持続可能な活動をしていくためにも、そして、美術作品を含む文化財を将来へ伝えていくためにも、必要なことなのです。
学芸員自身もこうした研修に参加して、最新の情報を得ておくことが大事だなとつくづく感じた5日間。これからも多くの方に美術館に足を運んでもらうために、まだまだ学芸員の学びは続きます。
(主任学芸員・飯島沙耶子)
 パッシブインジケータを使って展示室内の空気環境を測定する様子。96時間設置後の色の変化の様子から、空気の汚染レベルを判定します。
パッシブインジケータを使って展示室内の空気環境を測定する様子。96時間設置後の色の変化の様子から、空気の汚染レベルを判定します。