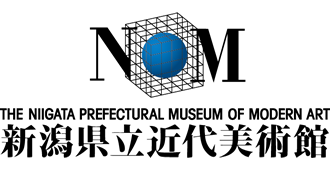学芸員コラム36 二つの蕗谷虹児展
2025年02月03日
昨年4月の異動により、万代島美術館から20年ぶりに当館へ戻ってきました。まもなく1年が過ぎますが、コレクションの展示作業や小学校への出前授業など、久しぶりの近代美術館勤務を楽しんでいます。はじめての「学芸員コラム」ですが、今回は大正末から昭和にかけて、可憐な少女像やモダンな女性像で一世を風靡した新発田市出身の画家・蕗谷虹児(ふきや こうじ)の展覧会について書いてみようと思います。
***
新潟県に2館ある県立美術館では、これまでに2度、蕗谷虹児の個展を開催しています。
■「少女達の夢と憧れ 蕗谷虹児展」
会場:新潟県立近代美術館 (長岡市所在。以下、長岡展)
会期:2004年10月9日~10月23日、11月7日 ※10月23日午後5時56分に発生した新潟県中越地震のため休止、その後11月7日のみ開館し終了。美術館の所在地は震度6弱を観測。
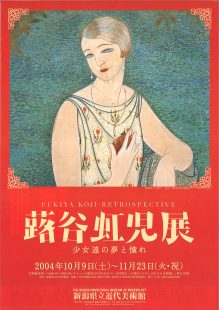 長岡展チラシ
長岡展チラシ
■「魅惑の線・輝く色彩 蕗谷虹児展」
会場:新潟県立万代島美術館 (新潟市所在。以下、新潟展)
会期:2007年7月28日~9月24日
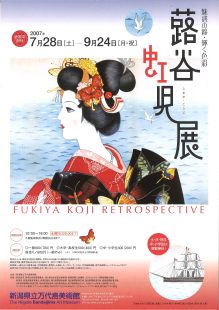 新潟展チラシ
新潟展チラシ
会場が違うとはいえ、数年の間に同一県の県立美術館で個展を複数回開催することは稀でしょう。まずは長岡展のお話から。
私の新採用時の勤務地は近代美術館でした(まだ万代島美術館がなかったころの話です)。学芸員となって数年目、そろそろ自主企画を出したい頃です。大正・昭和初期の大衆文化に興味のある自分が関わることのできそうな新潟の作家は……と探すうち、蕗谷虹児(1898-1979)にたどり着きました。主に女性や子ども向けの雑誌を活躍の場とした虹児は竹久夢二と同種の画家として扱われてきた感がありますが、最初期こそ夢二の画風に影響を受けていたものの、世代的には夢二より一回り以上も下で、活動時期もやや異なります。10代で上京し、日本画家の尾竹竹坡に師事。20代には女性雑誌の表紙や挿絵でスター作家となり、パリ留学時には藤田嗣治とも交流がありました。洗練された線と、透明感のある色彩による虹児の女性像はもちろん魅力的ですが、初期の濃密なモノクローム作品や、戦時中の名作童話の挿絵など、「こんなのも描けるの?」という驚きの作品も多いのです。決して夢二の二番煎じではない、彼の画業の全貌を見渡してみたいと思いました。
開催が決まり、一番はじめにご挨拶に伺ったのは、虹児のご子息である蕗谷龍生さんでした。長身でおしゃれ、どこか虹児の面影を漂わせる龍生さんは、少々口が悪いけれど、実はとても細やかな気配りをされる優しい方でした。新米学芸員の覚悟がどれほどのものなのか、はじめは厳しく様子見をされているようでしたが、最終的には公立美術館での初個展だと喜んでくださいました。主要な作品借用先となる新発田市と蕗谷虹児記念館からも快諾のお返事をいただき、その後、東京の美術館や出版社、個人宅への借用依頼も進みました。記念館へは作品の調査に何度もお邪魔して、当時のスタッフの方々にはずいぶんお手間をおかけしました。新発田市と新発田商工会議所の陽気な皆さんが開催に向けて大いに盛り上げてくださったのも、懐かしい思い出です。展覧会が多くの、そして様々な立場の人々と関わりながら出来上がっていくことを学びながらの作業でした。
そのようにして初日にこぎつけた展覧会ですが、会期がはじまって間もない10月23日の勤務後、東京からいらした龍生さんご夫妻と長岡駅前の洋食屋で注文をした直後、建物が大きな音を立てて揺れはじめ、店内の電気が消えて真っ暗になりました。これはただの地震ではないねと話しながら外に出ると、信号の消えた暗い道に大勢の人が座り込み、辺りは騒然としていました。遠方から来たお二人をその場に残していくのも心残りだったのですが、とにかく館と作品が心配で、通りかかったタクシーをつかまえ、まだ震源も、震度もわからない状態で、地面が揺れ続ける中を美術館へ急いでもらいました。
館の駐車場でタクシーを降り、その場にいた職員数名で、非常ベルが鳴り響く企画展示室を懐中電灯で照らしながら進みました。虹児の作品に被害がなかったこと、閉館後であり人的被害もなかったことは不幸中の幸いでしたが、固定していた壁面パネルやケースが大きく移動しており、揺れの激しさと恐ろしさを感じました。その後も余震が続いたため、展覧会は会期途中で終了することに決まりました。正直に言うと当時の記憶は断片的で、関係者への配慮や館内での事後処理等、果たして自分がその状況にきちんと対応できていたのか自信がなく、今でも所在ない気持ちになることがあります。
***
さて。その翌年に万代島美術館に異動になり、思ってもみなかったことでしたが、もう一度蕗谷虹児展を開催する話が持ち上がりました。龍生さんをはじめ、関係者や所蔵先にもご理解をいただき、長岡展とほぼ同じ作品リストで開催が叶うことになりました。作品は同じでも、会場が異なれば展示構成は新たに考えます。作品の見え方も、展覧会全体の印象も、ずいぶん違うものになりました。近代美術館の展示室はグレーのカーペット床。初期の日本画やパリ留学時の作品が会場にしっくりとなじみ、全体的に落ち着いた雰囲気でした。

 長岡展会場
長岡展会場
対して万代島美術館の床は明るい色のフローリング。昭和初期のモダンな作品のイメージと調和し、明るく軽やかな会場になりました。虹児の作品は小さなサイズのものがほとんどですが、展示室の広い空間ごと虹児の世界を楽しめるように、各章の入口には虹児の作品をイメージしたゲートを立て、壁面の大ガラスケースは雑誌目次の枠を拡大したシートで装飾しました。紙芝居、朗読会、コンサート、龍生さんとの対談などイベントも盛りだくさん。長岡展では予定していたイベントも中止になり残念な思いをしたため、新潟展ではあれこれ欲張りました。

 新潟展会場
新潟展会場
新潟展最終日の解説会では、長岡展からの経緯を話しているうちに声を詰まらせ、お客様から涙を拭くティッシュペーパーを手渡されるというお恥ずかしい事態に。これまで担当したどの展覧会にも思い入れはありますが、この二つの蕗谷虹児展は、震災による中止を経て、はからずも同じ作家の個展を近美万美の両館で開催するという経験をさせてもらった、特別な展覧会です。
***
虹児が没してまもなく半世紀になります。明治・大正・昭和という激動の時代を人気作家として生き抜いたことに加え、その人生も幼少期から波瀾万丈すぎてエピソードには事欠かない……この画家を、ドラマや映画の主役にしたら絶対に面白い作品になるのに!と思い続けています。ご興味のある方は書籍等でお確かめください。また、新発田市の蕗谷虹児記念館にもぜひ一度お出かけください。(専門学芸員 池田珠緒)
〈手に入りやすい参考文献〉
『蕗谷虹児(らんぷの本)』河出書房新社2013年
鈴木義昭『乙女たちが愛した抒情画家 蕗谷虹児』新評論2018年