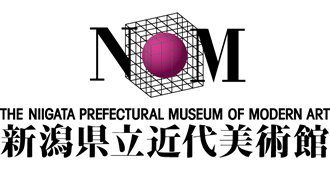学芸員コラム33 竹谷富士雄と矢部友衛
2024年09月24日
コレクション展第3期「没後40年 竹谷富士雄」(展示室2)では、本県五泉市出身の洋画家・竹谷富士雄(1907~1984)の1940~80年代の作品に加え、彼とかかわりのあった画家たちの作品を最後のコーナーに展示しています。旧制中学時代の同級生で、ともに絵画研究のため渡欧した鳥居敏文(1908~2006)、この渡欧時に滞在したアトリエの先住者であった山口薫(1907~1968)、帰国後の「池袋モンパルナス」時代に交友した桑原実(1912~1979)、そして二科展出品を機に師事した藤田嗣治(1886~1968)の4名です。
* * *
このコーナーでは紹介できませんでしたが、竹谷の画家としてのデビューに関与した重要人物に、本県村上市出身の矢部友衛(1892~1981)がいます。同時開催の企画展「日本が見たドニ|ドニの見た日本」(会期:8月27日~10月20日)では、矢部の滞欧作《習作》(1920年、図版1)を展示しています。彼は1918年(大正7)東京美術学校日本画科を卒業後、アメリカ経由でフランスに渡り、ナビ派の画塾「アカデミー・ランソン」に籍を置いた異色の経歴を持ちます。美校時代にはナビ派風の人物画を描き、パリではモーリス・ドニに直接師事しましたが、やがてキュビスムに近い作風を示したアンドレ・ロートに心酔、《習作》はまさにその頃、裸婦をキュビスム風に描いた作品だったのです。
《習作》が描かれたのと同じ年(1920年)、竹谷富士雄は県立村上中学校に入学し、程なくして、村上本町にいた同級生・鳥居敏文の家に下宿します。学校では絵の好きな学生のグループが作られ、竹谷は岸田劉生や草土社の影響を受けた図画担当の吉川純幹先生から石膏デッサン等を習い、画家となる決意を固めます。そして1924年(大正13)、中学5年生の時、矢部友衛と知り合う機会が訪れました。
矢部は村上中学の卒業生で、村上城跡の城壁裏、鳥居家の3、4軒先に実家がありました。彼は2年前の1922年(大正11)に帰国し、第9回二科展出品作《習作》等がヨーロッパの新傾向を示すものとして注目を集めました。そして、竹谷はこの時、矢部から立体派、未来派、ダダイスム等を紹介され、さらにプロレタリア美術運動への関心を持ったといいます。
1924年の矢部の動向を探ると、彼が結成に参加した「アクション」の分裂と解散、「三科」への再編という美術団体の目まぐるしい離合集散の渦中に彼がいたことがわかります。そのさなか、矢部は郷里の村上に立ち寄り、母校の後輩たちに向けて、最新の美術動向を熱く語ったのでしょう。竹谷らは、その後も矢部が帰郷するたびに面会し、雪の夜、瀬波温泉に宿泊していた矢部を訪ねるなどしました。また彼らは、町の農業陳列所を会場として、農機具を動かして低い唸りを立て、ブリキカンを投げつけ、激しい文字のポスターを町中に貼るなどの前衛的パフォーマンスを開催したといい、矢部からの影響は絶大なものでした。
竹谷は翌1925年(大正14)、村上中学を卒業し上京します。同年秋に開催された「三科」第2回展(東京自治会館)の出品者には、矢部、浅野孟府、岡本唐貴、村山知義、柳瀬正夢ら新興美術・プロレタリア美術を代表する画家たちに混じって、竹谷と鳥居の名前を見ることができます。竹谷は矢部からの推薦を受けて《コンストラクシヨン》を、鳥居は矢部とロシア人画家ワルワーラ・ブブノワの推薦を受けて《ボタンのあるコンストラクシオン》を出品しました。図様は分かりませんが、題名から、いずれも抽象的傾向の作品と想像されます。そして、これらが、両者にとっての展覧会初入選作だったと考えられます。
翌1926年(大正15/昭和元)、竹谷は法政大学経済学部に入学しますが、学業のかたわら、矢部が主宰するプロレタリア美術研究所に通い、「プロレタリア美術大展覧会」に作品を発表するようになります。1928年(昭和3)の第1回展(東京府美術館)には《スターリンの像》と題する絵画とポスター2点を出品、翌1929年(昭和4)の第2回展(同館)には「黒田雄二」の変名で、農民をモチーフとする油彩画《代議員をおくる》と、ポスターを出品しました(《漫画AB》は当局の検閲により出品撤回)。1930年(昭和5)の第3回展(日本美術協会)には「北村善作」の変名で《集合》、1931年(昭和6)の第4回展(東京自治会館)には同じく北村の名で《埼玉県吉見争議の勝利》と題する油彩画を出品しており、同展には鳥居敏文も《通信労働者は立上つた》という漫画作品を出品しています。
このように、竹谷と鳥居は、村上中学の同窓生であった矢部の導きによって新興美術やプロレタリア美術の世界に足を踏み入れたのでした。その後、彼らがヨーロッパ留学を志したのも、恐らく矢部からの触発によるのでしょう。二人は1932年(昭和7)夏、シベリア経由で渡欧します。その旅の途上、ドラマティックな出来事が起きました。竹谷が3年前のプロレタリア美術大展覧会に出品した《代議員をおくる》が、その後ソビエト連邦大使館の買い上げとなり、彼らがモスクワの美術館に立ち寄った際、この作品に偶然再会することになったのです。その後、この作品は、サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に所蔵されることになります。
竹谷らはまずベルリンに落ち着きますが、ナチスによる騒擾を避けてパリに移り、1935年(昭和10)の帰国まで同地に滞在します。滞欧中、日本国内ではプロレタリア美術運動への弾圧が強まり、彼らが帰国した時には、運動自体が完全に終息していました。自ずと矢部との関係は疎遠になり、竹谷は二科展(のち新制作派展)、鳥居は独立展への出品を重ね、それぞれ画壇での地位を固めていきます。戦争が激化すると、両者は「戦争画」の制作にも従事しました。
* * *
竹谷富士雄といえば、パリを中心とするヨーロッパの日常的風景を瀟洒な色彩で描いた画家(本間正義氏の言葉を借りれば「文字通り花の都パリを花のように描きつづけるカラリスト」)として知られています。ただし、この作風は1961~62年(昭和36~37)の再渡欧を経て確立されたものでした。それ以前の画業の前半期、竹谷は作風を様々に変転させましたが、そのなかで、彼が興味を持ち続けたのが「労働」というテーマでした。沖縄旅行を契機とする《絲満の親子》(1938年)や《壺つくりの女》(1940年、図版2)、女性をモチーフとする《市場の女達》(1952年)や《初秋(佐渡)》(1953年)、炭鉱に取材した《岩と人》(1957年、図版3)などは、いずれも労働者の姿を描いています。彼の親友である鳥居敏文もまた、労働者の姿を繰り返し画題に選びました。竹谷は後年「矢部さんとの出会いが、いかに大きな道標となっているか」と述べていますが、矢部と袂を分かった後も、青年時代に彼から教えられた視点を制作の基底とし続けたのは興味深いことです。
矢部友衛を初めとする様々な人物との出会いによって竹谷の画家としての道が開かれたこと、そして、彼の後年の作風が、激動の時代を乗り越えた末に獲得されたものであることに思いを馳せながら、竹谷の風景画が醸し出す美しい色彩を味わっていただきたいと思います。
(主任学芸員 長嶋圭哉)
 |
 |
 |
|
図版1 |
図版2 |
図版3 |
いずれも当館蔵